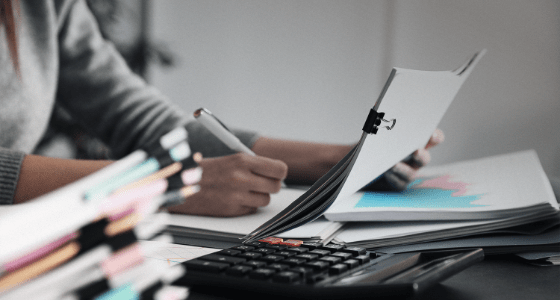Colla:J 車輪夢ものがたり

東京品川・戸越銀座商店街の近くに、白いフクロウを屋根に掲げるギリシャ神殿風建物があります。
家具モデラー宮本茂紀さん主宰の「ミネルバ」です。
知恵の女神ミネルバを象徴するフクロウには、宮本茂紀さんの椅子への想いが込められています。
龍村美術織物の依頼で行われた宮内庁の馬車修復作業を通し、椅子という道具は日本でどのように作られてきたか。
幕末からの歴史を振り返りましょう。
明治のはじめ椅子張りの元祖といわれるのが、大河原甚五兵衛と原安造(馬具安)です。
大河原は元々横浜のグランドホテルの調理人でしたが、備品の椅子や調度品の修繕を手掛けているうち、手の器用さをかわれ内装全般を手掛けるようになりました。
一方、原は幕末から横浜・本牧の辺りで馬具や馬車の内装を手掛け、明治元年頃にイギリス人から椅子張りを習ったそうです。
やがて2店とも元町へ店を構え、切磋琢磨しながら多くの名人が育ちました。(参考:全国椅子張同業組合連合会「創立五十周年記念誌」)


伊豆から東京に出た宮本茂紀さんは大河原の系統にあたり、昭和20 年代後半に斎藤巳之三郎親方に弟子入りしました。
当時は徒弟制度の時代で、親方の家に寝泊まりしながら主に高級家具の修復を手掛けていたそうです。
月刊「新潮45」(2011年2月号)に掲載されたビートたけしさんとの対談から、当時の職人達の暮らしぶりが活き活きと感じられました。
師匠から弟子へと伝えられてきた技が、迎賓館の家具や馬車の修復を支えているのです。
お話を伺ううちに宮本さんはもじゃもじゃとした見慣れない繊維を取り出しました。これは馬の毛です。
馬の毛を詰めたクッションに、椅子張り地をかぶせ縫製していきます。
ひとつの目を縫った後、半目ほど戻りながら縫っていくと、縫い目が開かないそうです。
クラシック家具によく使われるパイピング(たまぶち)は、クッションの形をかっちりとさせる効果があります。
この馬車は大正時代に作られましたが、クッションに使われた馬の毛はほぼそのまま再利用できるそうです。
張り地は「龍村美術織物」によって忠実に再現されたものを使います。
背のクッションは、馬の毛の上に綿を載せ、あらかじめ縫製した張り地をかぶせてから、ボタンの糸を下に通して固定していきます。
ボタンを使ったソファはめっきり減りましたが、そのぷっくりと盛り上がったフォルムには、他に変えられない豊かさを感じます。
縫製した張り地を馬車に取り付けていきます。馬車の内装は全て張り地で覆われ、きらびやかな空間へとドレスアップされます。
こうした伝統的な椅子張りの手法は、ルネッサンス期以降のヨーロッパで発達したのではないかと宮本さん。
明治のはじめ、その手法をゼロから覚えていったのは和家具(指物)職人ではありませんでした。
元は馬具や駕籠(かご)などをつくり、時代の変化に取り残されまいと、活路を見いだした職人達だったそうです。
宮本さんが弟子入りした芝界隈(現・新橋周辺)には、公官庁の仕事を受ける一流の職人が集まりました。
その伝統を受け継ぎながらも宮本さんは、デザイナーや自動車の椅子などを試作する日本初の「家具モデラー」として、常に時代の先端を走ってきました。


作業前には必ず現状の写真を撮っておき、クッションの中身まで含めて可能な限り忠実に再現します。
修復の仕事は伝統的な技術を継承するためにも欠かせないものなのです。
修復された年代によって材料や技術は少しずつ異なるため、この馬車は東京オリンピックのころ一度修復されたことが分かるそうです。
1台の馬車に歴史が積み重なっています。
宮内庁の馬車には様々なタイプがあり儀式に応じて使い分けられています。
この馬車は、大きく弧を描いた革製のベルトで客室を吊り下げ路面の凹凸を伝えにくい構造で、細かな部分まで工芸品のように仕上げられていました。
一方座面のクッションは、通常のソファよりも固めに仕上げられ、ゆりかごのようなゆったりとした乗り心地が想像できます。
ステップは折り畳んで収納できるようになっています。内装の終った後は、別の工場で外部に漆を使って仕上げるそうです。
内装と並行して屋根の修復作業を進めます。屋根の内側に布を張っていき、最後に外側から革をかぶせます。
この屋根は折り畳み式で中央から外れるようになっています。
屋根に張り地をかけ、座面などの取り付けを終えると、きらびやかな光に包まれた空間が生まれました。
都心を走る工芸品ともいえる、二頭曳き座馭式(ざぎょしき)の儀装馬車。
日本に着任した大使へ伝統文化を伝えるという、国際親善のための大切な役割も担っています。

ミネルバのリストア(修理・修繕)のすすめ
弊社ではこれまでに数多くの文化財やそれに近い家具や椅子などの修復や、復刻、張替えに関わらせていただいております。
お客様の歴史や想いを形として残していく手伝いをすること、「歴史や背景」に触れることを大切にしたいと考えています。
[su_button target=”_blank” style=”flat” background=”#cccc34″ size=”5″ url=”https://www.minerva-jpn.co.jp/space_furniture/furniture/restore/”]リストア(修理・修繕)についてはこちらから[/su_button]
Colla:J(外部サイト)
[su_button url=”http://collaj.jp/data/magazine/2011-03/index.html” style=”flat” background=”#CCCC33″ size=”4″ center=”yes” radius=”5″target=”_blank”]Colla:J[/su_button]
– Link -リンク
[su_button target=”_blank” style=”flat” background=”#cccc34″ size=”5″ url=” https://www.minerva-jpn.co.jp/special/collaj/”]特設サイト[/su_button]